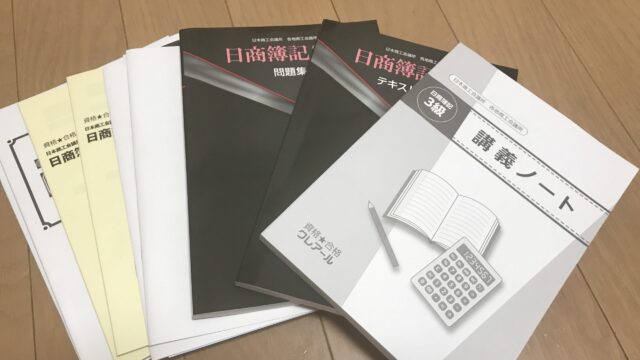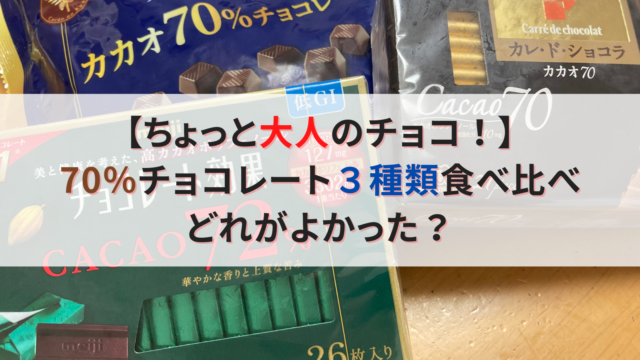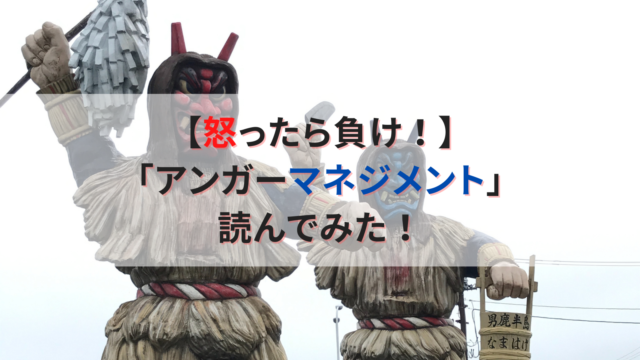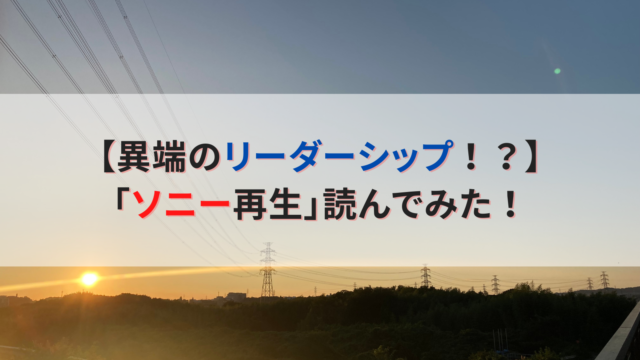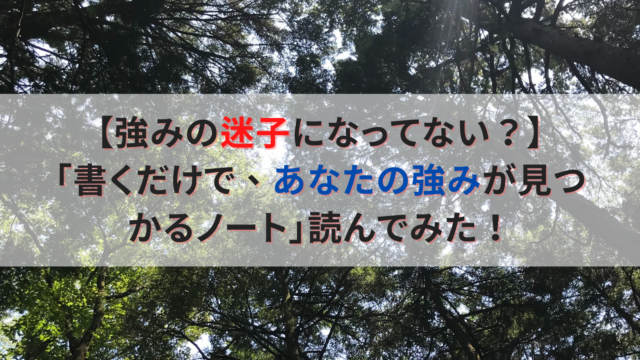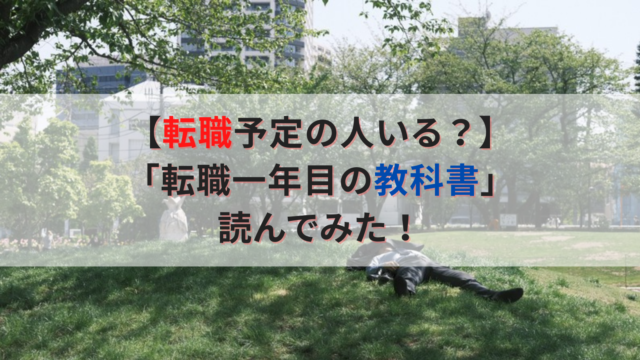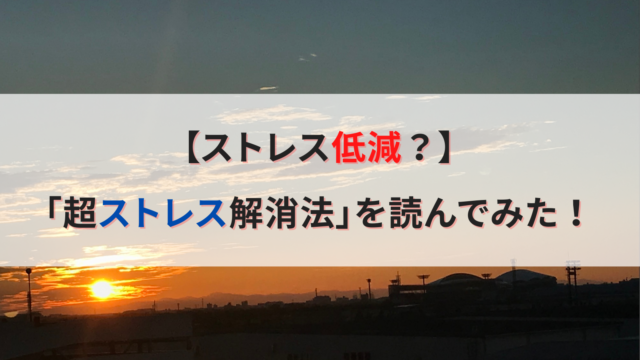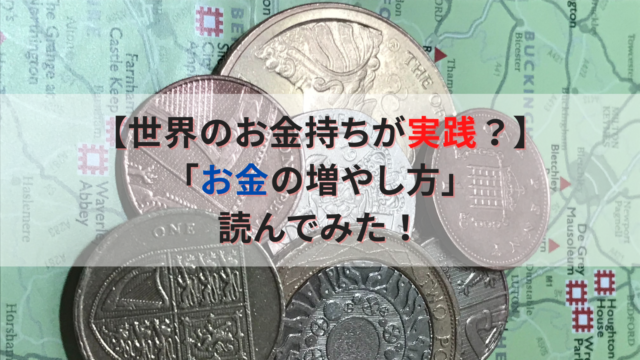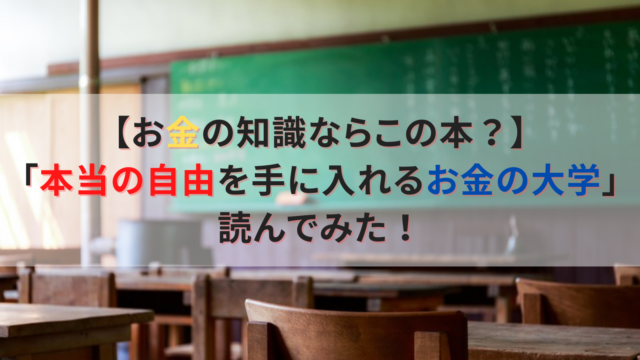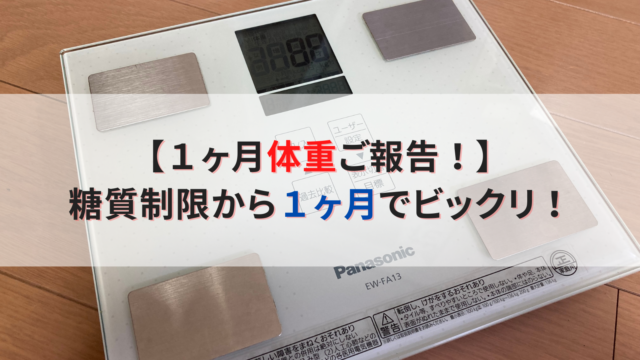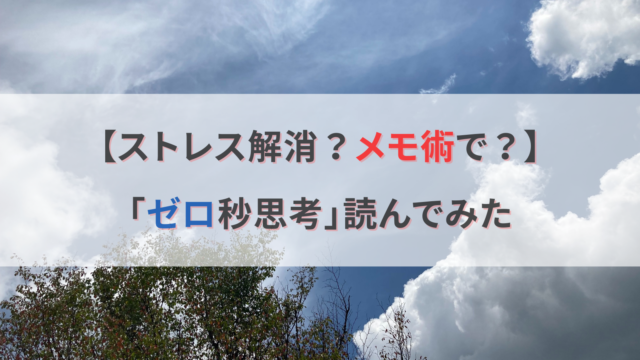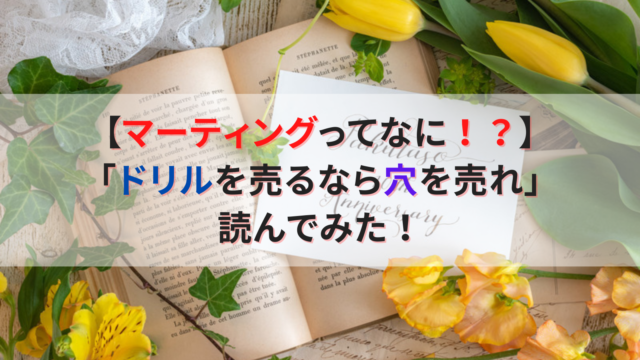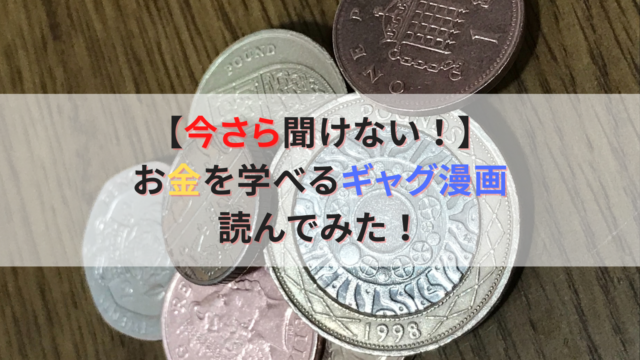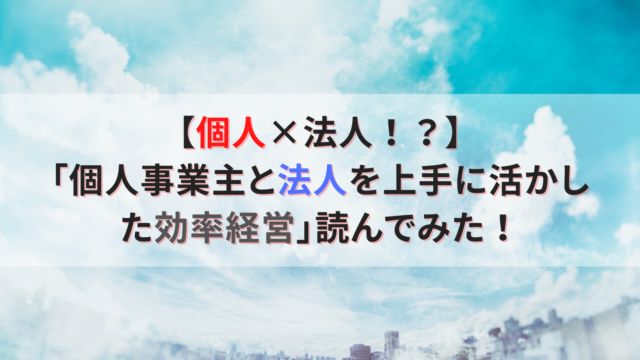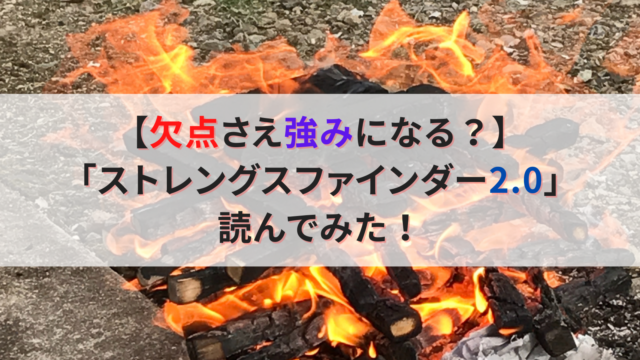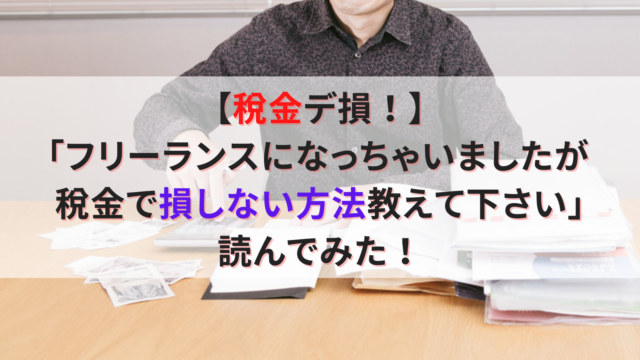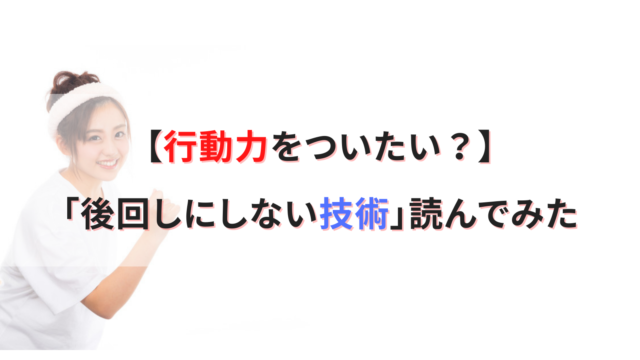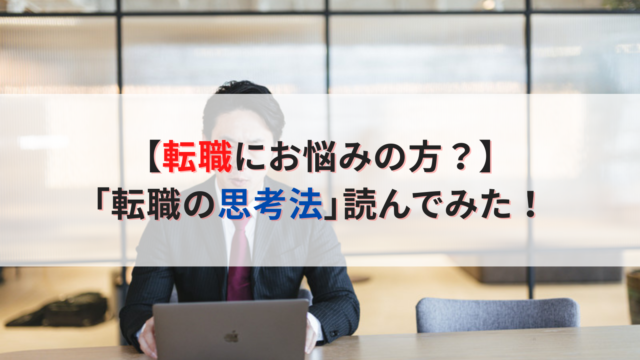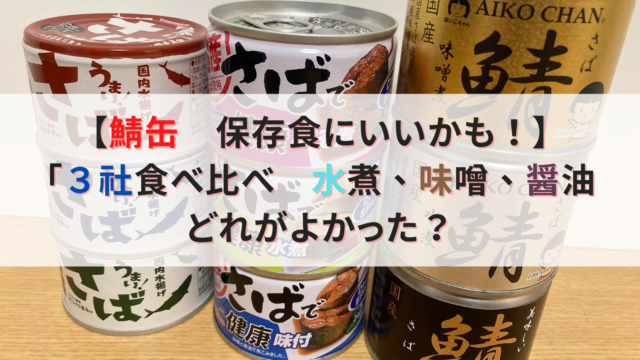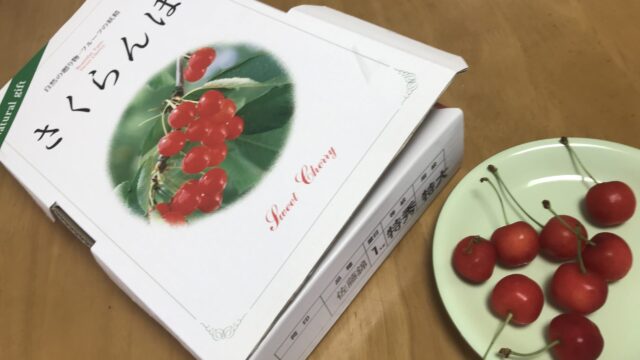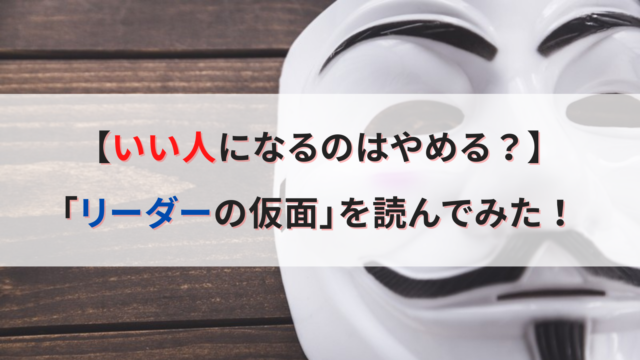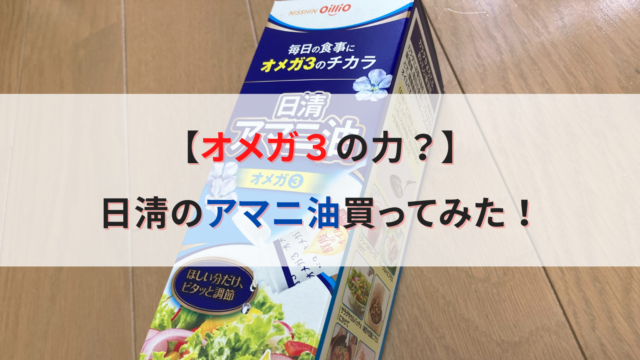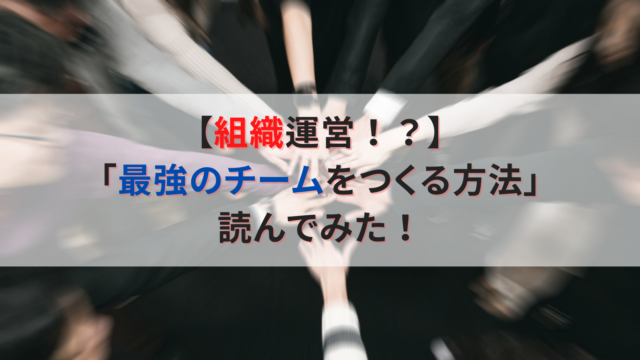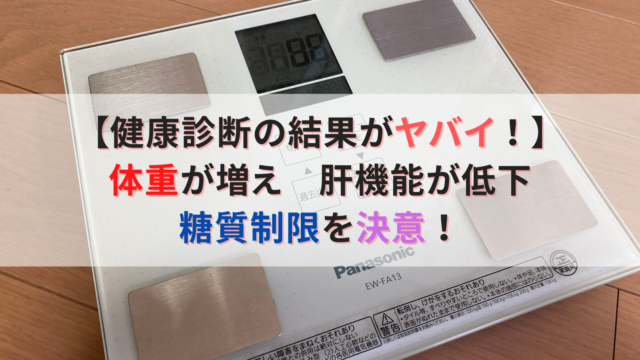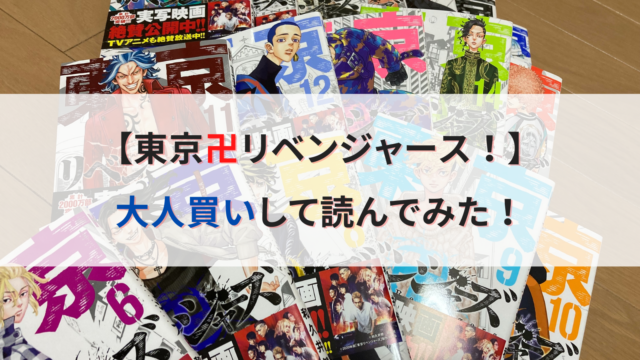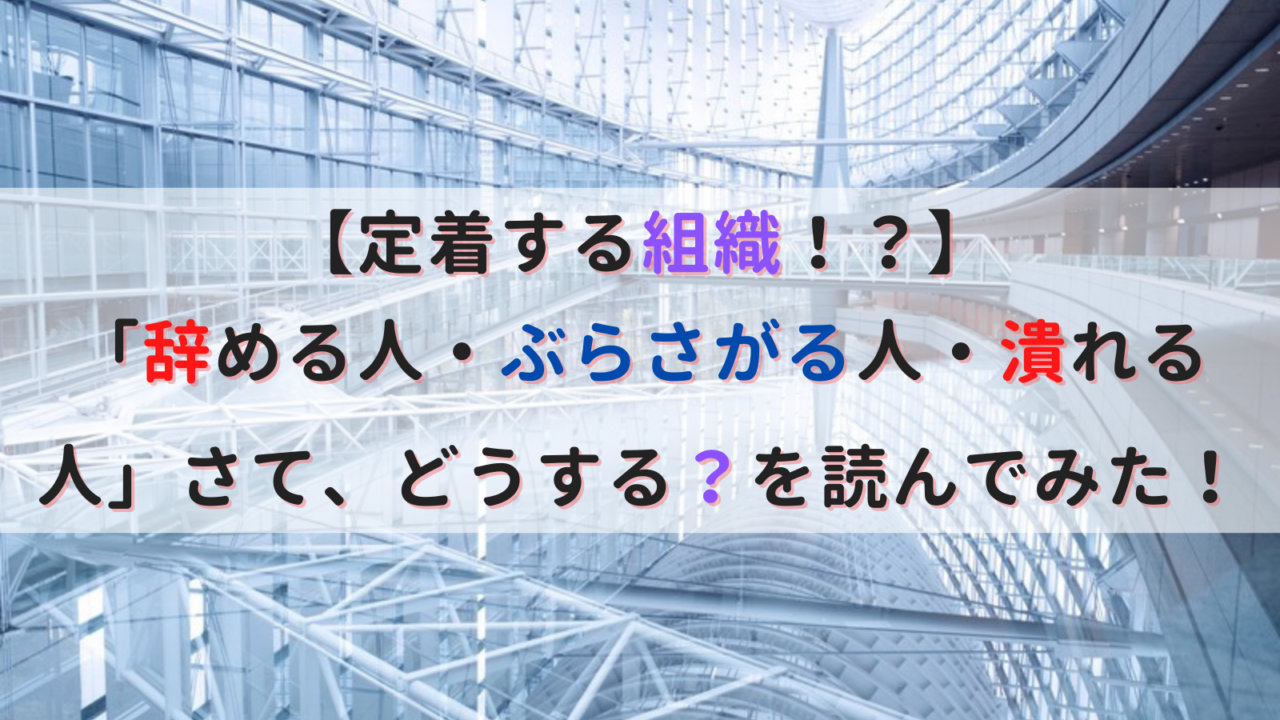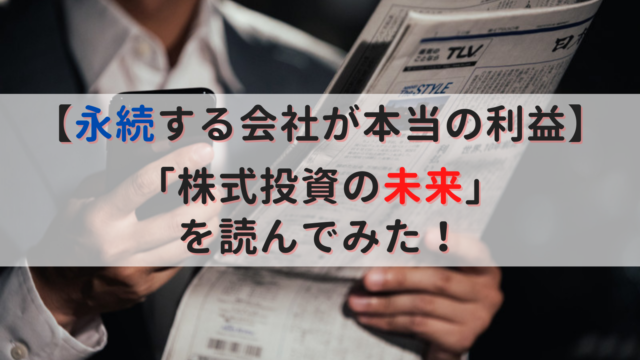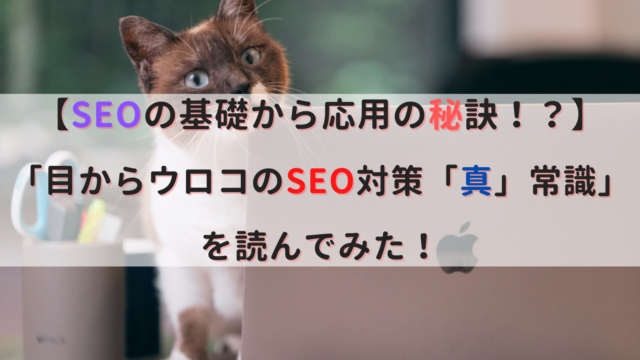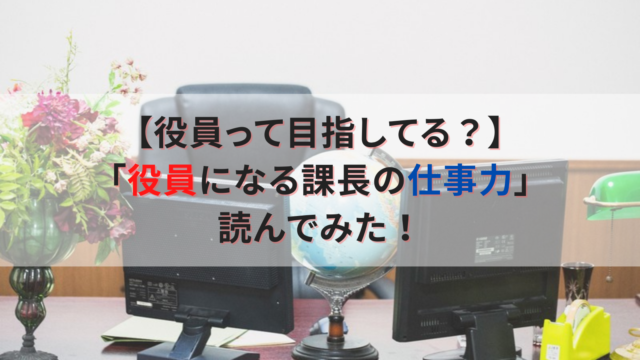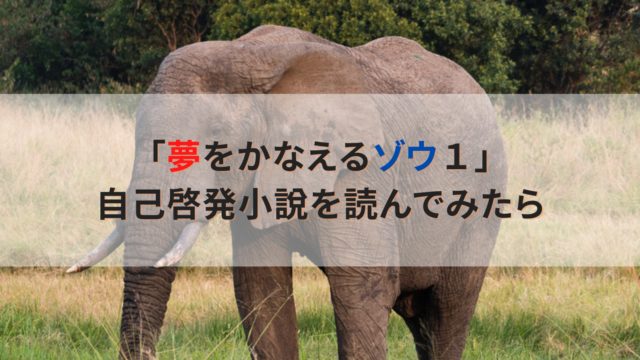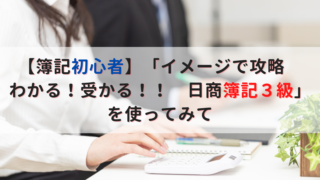「辞める人・ぶらさがる人・潰れる人」さて、どうるする?(著:上村紀夫/クロスメディア・パブリッシング)を読んでみた!
社畜生活で感じていた、慢性的な人手不足! 心身ともに疲れが溜まっている人、人間関係トラブル 組織にぶらさがる上司、不満の声がたない職場、マネージャー層が疲弊などとても共感できました。
今日も、よろしくニャン! 組織の問題ニャンね!
今日もよろしく、ねこぱん 組織の問題はとても痛感しているので、興味があり
なんとかしたい気持ちあり、モヤモヤする気持ちを等を無くすにはどうしたらいいのか?
そんな思いで、組織関連の本を読んでいます。
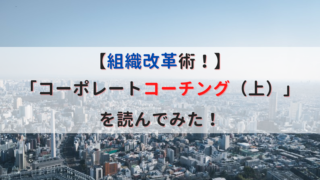
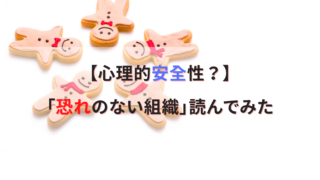
この本のポイント:共通する原因はマイナス感情の蓄積
不平、不満の生まれるメカニズムを知る
不平、不満を取り除くための「ターゲットの絞り方」
産業医として3000人を以上の社員の声、年間1000以上の従業員の意識調査、経営者、管理者とのディスカッションなどから、組織の活性化させる戦略をお伝えしています。
不平不満はよくあるニャンよ!
そうんだね、辞める人、ぶら下がる人、潰れる人を間近にみていたので、自分もいつその3つになるか不安だよ。
だから、自分から変わる! 変わるためには、まずは知識を身につける!
行動力は大事、でも、ただ行動する前に考える、しかし考えこまない、考えをループさせない事、とにかく紙にとりあえず書き出すといいです。そして、行動と思考のバランス感覚が重要です。
でもそのバランスは自分で決めていい、本当になりたい人になる。忖度しなくていい。そのために自分を知り考える、そして、ちょっと自分の外の世界を知りちょっと行動することで可能性が広がるかなと思います。
この本で気になった3つの事

①:個人で変わる労働価値
個人でもちろん、変わるのが、労働の価値観、自分自身の歳、健康状態、家族背景でも変化があり、ましては、個人個人の、状況での労働の価値感が違ってい当然です。
まずは、労働価値は変化し、また、個人個人で違うことを認識することが重要
人それぞれ労働価値が異なり、しかも変化するという前提を把握せず、施策ばかりを追いかけると空ぶるというのはこういった理由があります。
「辞める人・ぶらさがる人・潰れる人」さて、どうるする? P54(著:上村紀夫/クロスメディア・パブリッシング)ISBN978-4-295-40395-1 (税別1580円)
価値観では、マクロとミクロの2種類の視点から考える
- 時代、社会変化などのマクロ的視点
- 個人の局所的(体調、年齢、結婚等)要因のミクロ的視点
労働価値が人それぞれ違うと、心に思うと、少しは楽になれます。
労働の価値は違うし、押し付けるのも良くないです。押し付けられることもありますが、淡々と仕事をしましょう、そして、なるべく近づかない、いきなりではなく、JOJOにフェードアウトを心がける。
そうはいっても、仕事なので、どうしてもって時は、本当は価値感の違いは難しいですが、ひとつの方法は、自分が変わるしかないので、自分の価値観の抽象度を上げ、相手の価値観とひとつにすることですが、出来る場合と、したくない場合があるので、それは、状況に合わせてです。
やりたくない事は、極力しないことがいいと思います。 なので、JOJOにフェードアウトするのがいいのかな、そして、フェードアウトしても大丈夫なように、必要な、自分自身の爪を磨くことが大切だと思います。
労働価値はひとそれぞれニャンね!
そうなんだよ!労働価値はひとそれぞれだね!
②最悪なのは「不必要なダイバーシティ」
昨今、ダイバーシティ「多様性」については、よく組織には、必要と言われていが、まさに、不必要なダイバーシティは良くはないのではと思います。
もちろん、ガチガチの一辺倒の価値観では、さすがにちょっと変化に対応できる組織を作るのは難しいですが…
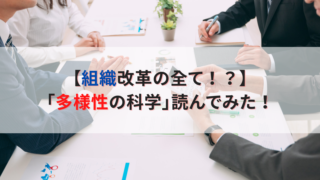
ここでは、労働価値の違いの軸とスキル、経験、思考法の違いの軸から、不必要なダイバーシティと定義(労働価値の違いが大きく、スキル、経験、思考法の違いが少ない場合)しています。
働く目的が、全く違い、労働価値の違いによるギャプだけが大きくなると、マイナス感情が生まれやすくなる。
労働価値の違いによるギャップが広がってマイナス感情が蓄積すると、定着率が低下し、組織運営は困難を伴います。
「辞める人・ぶらさがる人・潰れる人」さて、どうるする? P64(著:上村紀夫/クロスメディア・パブリッシング)ISBN978-4-295-40395-1 (税別1580円)
ここで重要なのは、会社の労働価値を自分とあっているか? 就職するにも、転職するにもとても重要です、価値観が大事です。 だから、自分の価値観と正直に向きあうといいと思います。
でも、ちょっと私は苦手です。正直、本当の自分を知ることが怖いことがある、理想とはちょっと違ったり、でも大丈夫、人は、光と闇を抱えているので、そうゆうものです。だからこそ、 自分の心は自分で作る、自分の価値観は自分で作る。自己責任です。 どうせなら、心からワクワクする、なりたい自分になろう~。
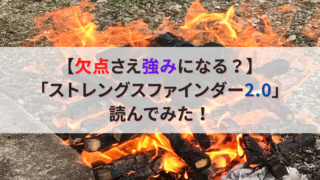
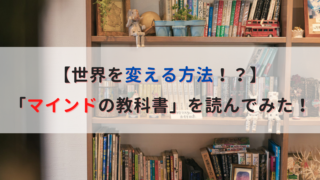
多くの会社では、ビジョン、パーパスなど掲げていいますが、本当に、浸透しているか微妙であると思います。オーナーの経営者は本気で思っていますが、ナンバー2、3等のサラリーマンの役員などは、本気で思っていない場合も多いのでは?
後にででくるが、タレントマネジメントをしっかりする必要があるね
多様性は重要でじゃないニャンか?
重要だけど、労働価値が違いすぎるとよくないね、スキル、経験など多様性があるといいかな
③マーケティングと組織戦略は共通点が多い
マーケティングと組織戦略をこの本は結びつけてくれました。
組織戦略とはいわば「社内マーケティング」とも言えます。
「辞める人・ぶらさがる人・潰れる人」さて、どうるする? P173(著:上村紀夫/クロスメディア・パブリッシング)ISBN978-4-295-40395-1 (税別1580円)
- 顧客の心を読んで商品を買ってもらうのが、マーケティング
- 社員の心を読んで組織を活性化させるのが、組織戦略
マーケティングのように、セグメント(細分化)や、ターゲティング、ポジショニング等を組織戦略にも使用していくこと大切
人材を細分化して、ターゲットを決め対策を打ち出すこと、ここでは、人材を5分類、優秀、ハイポテンシャル、立ち上がり、普通、ぶら下がり、に分ける、また、3つの要因として、働きがい、働きやすさ、心身コンデションなどから、対策の優先順位を決めていくことが大切
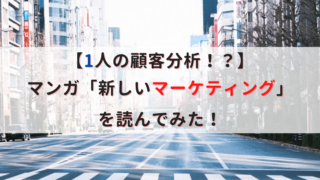
マーケティングと組織戦略はにているニャン!
そうだね、細分化して、ターゲット決めてやるといいよね
まとめ
「辞める人・ぶらさがる人・潰れる人」さて、どうるする?(著:上村紀夫/クロスメディア・パブリッシング)を読んでみた!
社畜生活で感じていた、慢性的な人手不足! 心身ともに疲れが溜まっている人、人間関係トラブル 組織にぶらさがる上司、不満の声がたない職場、マネージャー層が疲弊などとても共感できました。
すべては、マイナス感情が重要ってことが分かった。たしかにその通りであると感じていました。
また、対策に、マーケティングと同じように、セグメント化、ターゲティング、ポジショニングなどで、とても興味深く、そしてためになりました。
今日も、最後まで、読んで下さりありがとうございました!
今日も、最後までありがとニャン!